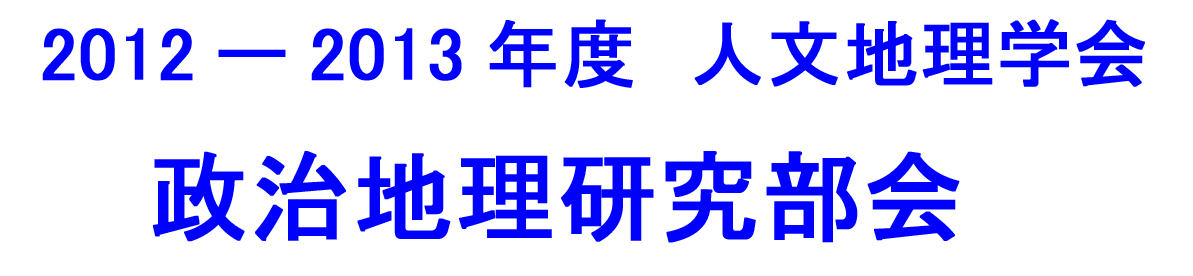
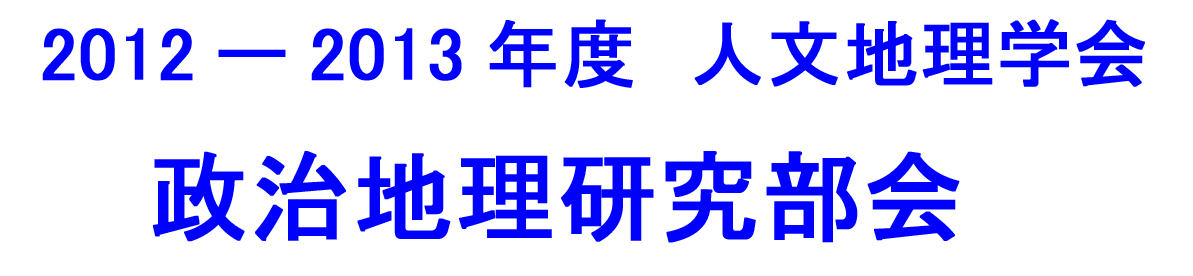
最終更新日:2013年11月22日
第7回 政治地理研究部会 研究会(部会アワー)報告
本報告はテーマを「地政学・政治地理学を学ぶ(その2)とし,8月3日に行われた第6回研究会に引き続いて, コーリン・フリント著(2011)『地政学入門 Introduction to Geopolitics』(第2版)を取り上げ,英語圏地政学の最近の特徴について報告した。
地政学は,スウェーデンの国家学者チェレーンによって,国家学の一分野(国家と領土に関する分野)として20世紀初頭に成立した。その後,ドイツでハウスホーファーらの地理学者によって興隆し,日本でも十五年戦争期に国策迎合的な運動として活発に展開されたが,敗戦とともに消滅し,戦後はネガティブタブーとされてきた。しかし,1980年前後に,地政学の世界的なブームが起き,日本でも地政学書の刊行が相次いだ。このブームは欧米では地政学の復活と形容され,地理学者による国際政治・経済への関心の高まりにつながったのに対して,日本では「悪の」という形容詞が強調された大衆向けのブームにとどまり,地理思想史的な関心を除けばアカデミズムにおける関心は高まらなかった。このあたりの理由として,発表時に読み上げた原書房社長成瀬雅人氏からのメッセージにも記されていたように,日本の出版界における左翼偏重的な傾向がある。
1990年代以降,グローバル化とともに地政学に対する関心はさらに高まり,欧米ではさまざまな地政学書が地理学者によって出版されるようになった。ここで紹介するコーリン・フリント(2011)『地政学入門』(第2版)は,序章を含めて10章から成る。「序章」では地政学とはどのような学問なのかについて分かりやすく説明した後地政学の簡単な歴史を紹介する。次いで「第1章 地政学を理解するための枠組み」では,場所・スケール・地域など地理学の基本概念と政治との関わりを述べる。「第2章 地政的行為:地政的コードという概念」では,地政的コード(対外政策を方向付ける体系)という概念を導入し,同盟国と敵対国への対処の仕方や米国のグローバルな地政的コードとそれに対抗する国や国以外の主体を取り上げている。「第3章 地政的行為の正当化:地政的行為の表象」では,地政的コードを国民に対して正当化すること,すなわち表象の議論がリーダーズダイジェスト,映画,米国大統領による一般教書演説などの事例を用いて説明されている。「第4章 地政学をナショナル・アイデンティティに埋め込む」では,地政的行為の実践と表象において不可欠な要素であるナショナル・アイデンティティとナショナリズムについて述べるとともに,ジェンダー的観点からの考察も試みている。「第5章 領域的地政学:世界政治地図の揺らぐ基礎?」では,領域と境界について扱っている。領域の構築や安全保障などを述べた後、国境紛争の事例としてパレスチナとイスラエルおよび朝鮮半島の富津の事例を紹介する。「第6章 ネットワーク地政学:社会運動とテロリスト」では,グローバル化に伴って国境を越える流動や移動に焦点をあて,具体的事例として社会運動やテロリズム,サイバー戦争などを取り上げて説明する。「第7章 グローバルな地政的構造:枠組みを形成する主体的行為」では,モデルスキーの世界的リーダーシップモデルを用いて、今日の米国が衰退段階にあることを主張するとともに,EUなどの行為者をこのモデルの中に位置づけ,このモデルの限界と可能性について検討している。「第8章 環境地政学:安全性と持続可能性」では,初版では扱われていなかった地球温暖化に代表される環境問題を人類の問題とし,環境安全保障が必要なことを主張している。「第9章 乱雑な地政学:作用と多様な構造」では地政学の複雑さと乱雑さが示される。ここでは武器としてのレイプを取り上げるとともに,ジャム・カシミール紛争やニューヨーク州軍の事例を用いて,本書の基本的枠組みである構造と主体的行為の相互作用を俯瞰しようとする。そして,主体的行為は構造により制約を与えられると同時に可能性をも与えられることが強調されている。
以上紹介したように,本書は構造化理論に依拠し,構造と主体的行為との相互作用として地政的行為を説明する点に他の地政学書にはない視点を有している。また,世界システム論にも依拠しており,グローバル・ナショナル・ローカルという多元的なスケールで対外政策を理解しようとするのも本書の特徴である。さらに,人文地理学の基本的概念との関係を踏まえた地政的行為の説明となっていることから、読者は地理学的方法論に基づいて地政学事象を学ぶことができる。ともすれば,リアルポリティークが強調されがちな日本の地政学において,本書は地理学というディシプリンに基礎を置く重厚な入門書である。
■質疑応答
■司会所見
以上のように,終了時刻を30分ほど超過して活発な議論が行われた。最後に,司会者が,日本の政治地理学および人文地理学においては,国家以上のスケールへの視角が決定的に不足しており,今後,こうした国家以上のスケールを研究に積極的に取り組む必要があるとまとめた。
たまたま報告者は,同日午後の特別研究発表で,「経済のグローバル化と地理学」と題された特別研究発表を聴いたが,報告者の宮町良広氏も,日本の経済地理学に望まれることは国家以上のスケールの分析だと指摘されており,奇しくも同様な結論が得られたのは偶然とは言え興味深いものだったことを付記しておきたい。
(出席者:18名,司会者:山﨑孝史,記録:高崎章裕)
人文地理学会ホームページへ戻る
本ホームページに関するお問い合わせは、tfutamur[at]mail.doshisha.ac.jpまでご連絡下さい。