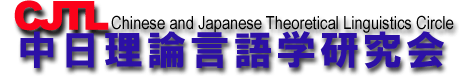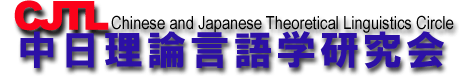|
第66回中日理論言語学研究会のご案内
2025年12月23日
中日理論言語学研究会 事務局 星 英仁
寒冷の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
第66回中日理論言語学研究会を、下記の通り開催いたします。ご多忙の時期とは存じますが、多くの方々のご参加をお待ち申し上げます。
記
日時:2025年1月25日 (日) 午後13:30から17:30まで
会場:同志社大学大阪サテライト・キャンパス(※対面開催のみ)
〒530-0001 大阪市北区梅田1-12-17 JRE梅田スクエアビル17階
TEL:06-4799-3255
アクセス:https://www.doshisha.ac.jp/information/campus/access/osaka_o.html
参加方法:参加を希望される方は、下記のURLまたは添付したチラシのQRコードにアクセスし、2025年1月18日(日)の21時までにGoogle フォームにて参加申込書をお送りください。なお、会場の収容人数の関係上、参加には人数制限がございます。上記日時より前に受付を終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
上記日時より前に受付を終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
Forms URL:https://forms.gle/mZw9zHsRZsdoQ2nE6
************************************
講演者(敬称略)及び題目・要旨:
発表1:「現代中国語における垂直系時間名詞(句)の起点フレーム」
発表者:下地早智子(神戸市外国語大学)
要旨:
現代標準中国語において空間の対立軸を指す形態素を構成要素とする時間詞には、“前/后”を用いる系列(H系)と“上/下”を用いる系列(V系)がある。「メタファー」とは、具体的な身体経験(起点フレーム)を未知の抽象的なものに写像することにより、その抽象的なものに関する構造的な知識(目標フレーム)を創造するやり方であると考えられている。本発表では、V系の起点フレームに関する従来の有力な仮説を検討し、H系とどのような認知的対立がある(あった)のかを確認する。なお、本発表は日本中国語学会第75回全国大会における招待発表とほぼ同じ内容であるが、当日接続トラブル等で十分説明できなかった内容について補足したい。
発表2:「現代中国語「是…的」構文の成立条件の再検討:虚詞「的」の語彙的属性に基づく理論的分析」
発表者:郭楊(関西大学)
要旨:
本発表では、現代中国語の「是…的」構文の成立条件を、生成文法の立場から理論的に再検討する。従来研究の多くは、「是…的」文が容認されるか否かを句構造(構文配置)の差異に求めてきた。しかし、私は生成文法の語彙中心的な立場に立ち、文の可否は句法構造そのものではなく、文を構成する語彙項目――とりわけ虚詞「的」――の個別的な文法属性・意味属性の相容性によって決定されると考える。本研究では、同じ「是…的」形式であっても容認度が異なる現象を説明するために、「的」が担う文法的・意味的機能を詳細に分析し、それをLinker・Nominal・Aspect・Answerの四種に類別した。特に「是…的」文における アスペクト的「的」 に注目し、その選択制約が述語のアスペクト特性や文の情報構造といかに相互作用するかを明らかにする。
以上を通じて、「的」を独立した語彙項目として捉えることで、「是…的」構文の文法性判断に関する新しい説明原理を提示する。
発表3:「也談日語作為名詞型語言的基本特徴」
発表者:彭広陸(吉林外国語大学)
要旨:
動詞与名詞作為詞類体系中的両大核心類別,在不同語言中呈現出多様化的語法語用功能,其作用的差異有時頗爲顕著。劉丹青(2010)基于語言類型学提出:漢語是一種動詞型,或称動詞優先的語言;英語則是一種名詞型,或称名詞優先的語言。二者分別代表了詞類語法優先度上相対立的両種語源類型。以往也有一些学者提出過日語属于名詞型語言。本研究从形態類型、詞類分布、名詞謂語句的使用、話題化以及省略等不同的角度対日語和漢語進行比較,在此基礎上指出从整体傾向上日語可視為“名詞型語言”,但与英語又存在類型学上的一些差異。可以説日語在語言類型論領域具有独特的研究価値。
********************************************************
本年も皆様の温かいご支援とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。来年も変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
事務連絡及びお問い合わせ:
中日理論言語学研究会事務局
〒610-0394 京都府京田辺市多々羅都谷1-3
同志社大学文化情報学部 星研究室(夢告館711)
TEL・FAX:0774-65-7701
URL:http://www1.doshisha.ac.jp/~cjtl210/index.html
email:hhoshi@mail.doshisha.ac.jp(星)
|