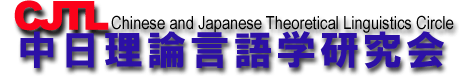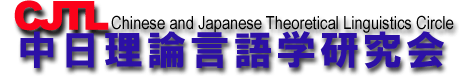|
第65回中日理論言語学研究会
日時:2025年9月28日(日)
場所:同志社大学大阪サテライト・オフィス
ご報告:
先にご案内させていただきました第65回中日理論言語学研究会は、9月28日(日)に同志社大学大阪サテライト・オフィスで開催され、46名の方々にご参加いただき、成功裡に終了いたしましたことをご報告申し上げます。
今回の研究会では、日本語・中国語を中心とした言語学的課題を扱い、理論的な観点から比較・考察を行う場として開催されました。三件の発表を通じて、構文・アスペクト・疑問表現・照応といった多角的なテーマにアプローチし、
言語の普遍的特性と地域的特質を検討することを目的としました。
益岡氏は、日本語における存在型アスペクト表現(テイル構文・テアル構文)を対象に、その体系性を論じました。特に「ナル・スル並立」という日本語の特性が、存在動詞アル・イルの能動性/所動性の区別に深く関わることを指摘しました。さらに、存在型アスペクト構文には動詞のテ形が密接に関与し、アスペクトはテンスだけでなくヴォイスとも関係する文法現象であることを提案しました。
林氏は、中国雲南省のチノ語(シナ・チベット語族)における疑問文の表現形式を再検討しました。文末助詞の使い分けが真偽疑問文・疑問語疑問文の区別だけでなく、述語の名詞性/動詞性や焦点範囲に依存する点を指摘しました。さらに、チノ語の特徴をロロ・ビルマ諸語および漢語方言の疑問表現と比較し、東アジア諸語に共通する文末助詞・重複・A-not-A構文などの疑問ストラテジーを類型論的に位置付けました。
劉氏、孫氏、宋氏は、Fauconnier (1994) のメンタル・スペース理論を発展させた東郷 (1999, 2000) の談話モデルを用い、日本語と中国語の照応現象を分析しました。孫氏は「自分」と“自己”の総称用法を比較し、中国語では量化表現や談話文脈の制約下でのみ成立することを明らかにしました。宋氏は中国語の連想照応を分析し、それが「抽象」から「具体」への動的プロセスであり、文脈情報との緊密な結びつきが不可欠であることを示しました。全体として、談話モデルが多言語において有効な分析枠組みであることを主張しました。
三件の発表はいずれも「形式と意味の相互作用」を焦点とし、アスペクト(時間的構造)、疑問表現(焦点構造)、照応(指示構造)という異なる現象を取り上げながら、文法・談話・語用の各層における体系性を議論しました。とりわけ、日本語と中国語を架橋する比較的視座が多く提示され、東アジア言語に特有の現象を普遍文法との関係で捉え直す試みが印象的でした。
次回の第66回中日理論言語学研究会は、2026年1月に開催予定です。詳細は追ってご連絡させていただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
<発表者及び発表題目(敬称略、順不同)>
(発表概要(PDF)を公開いたします)
益岡隆志(神戸市外国語大学名誉教授):
「日本語の存在型アスペクト形式の構文」(PDF)
林範彦(神戸市外国語大学):
「チノ語の疑問表現ストラテジーとその東アジア諸語の類型的位置付け」(PDF)
劉驫(大阪大学)、孫盈盈(大阪大学大学院生)、宋雨潤(九州大学大学院生):
「談話の世界における照応の諸相−再帰代名詞と連想照応をめぐる事例研究−」(PDF)
※著作権は発表者にあり、引用される場合「中日理論言語学研究会第65回研究会発表論文集」を明記すること
|