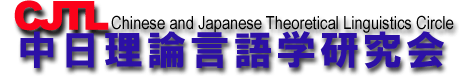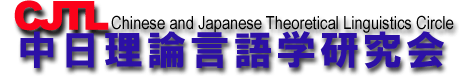|
第63回中日理論言語学研究会
日時:2025年01月26日(日)
場所:同志社大学大阪サテライト・オフィス
ご報告:
関係者の皆様へ:
先にご案内させていただきました第63回中日理論言語学研究会は、1月26日(日)に同志社大学大阪サテライト・オフィスおよびオンラインで開催され、50名の方々にご参加いただき、成功裡に終了いたしましたことをご報告申し上げます。
伊藤さとみ氏は「反語文の成立条件」について発表し、反語文における否定極性成分の認可および反語文への応答形式をもとに、英語・中国語・日本語の反語文が成立する条件を提案しました。英語では、反語文が表す陳述命題は前提の一部としてアクティブな情報状態にないため、否定極性成分の認可は前提において行われると指摘しました。中国語では、反語文の陳述命題は書面語では前提の一部となるが、口語では新たに作られた情報状態に属するとし、否定極性成分の認可は前提においてのみ行われることを示しました。さらに、日本語では、反語文の陳述命題が新たに作られた情報状態に属すること、また完全否定極性成分の認可は新しい情報状態が形成される前に行われなければならず、否定語にアクセスできないため認可されないことを提案しました。
塚本秀樹氏・許文傑氏は「広東語・北京語・日本語・朝鮮語における副詞表現の対照言語学的研究―特に動詞に後置された要素の文法化に着目して―」について発表し、これらの言語における副詞表現の類似点と相違点を比較検討しました。その結果、広東語の副詞表現は日本語と、北京語の副詞表現は朝鮮語と、それぞれ非常に類似していることを結論づけました。また、形態論的言語類型論の観点から、広東語と北京語(孤立言語)、日本語と朝鮮語(膠着言語)の関係を踏まえつつ、異なる類型に属する言語間の関連性について議論を行いました。
沈力氏・楊苗苗氏は「中国語の複合動詞はどこで形成されるのか―北京官話と江淮官話の比較から―」について発表し、語の緊密性を示す連続変調に関する違いを指摘しました。具体的には、北京官話では連続変調が統語部門の階層性制約を受けるのに対し、江淮官話(連雲港方言)ではその制約を受けないことを明らかにしました。また、北京官話の合成動詞と江淮官話の合成動詞はいずれも統語部門で分離可能であるが、北京官話ではさらに形態的結合体を形成するのに対し、江淮官話では形態的結合体を形成しないことを述べました。これを踏まえ、北京官話の合成語は統語部門で形成されるのに対し、江淮官話の合成語は音韻部門で形成される可能性があることを示唆しました。
本研究会では、フロアからも多くの質問やコメントが寄せられ、活発な議論が交わされました。非常に盛況な会となりましたことを、改めてご報告申し上げます。
次回の第64回中日理論言語学研究会は、5月に開催予定です。詳細は追ってご連絡させていただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
<発表者及び発表題目(敬称略、順不同)>
(発表概要(PDF)を公開いたします)
伊藤 さとみ(お茶の水女子大学):
「反語文の成立条件」(PDF)
塚本秀樹・許文傑 (関西外国語大学):
「広東語・北京語・日本語・朝鮮語における副詞表現の対照言語学的研究―特に動詞に後置された要素の文法化に着目して―」(PDF)
沈力・楊苗苗(同志社大学):
「中国語の複合動詞はどこで形成されるのか―北京官話と江淮官話の比較から―」(PDF)
※著作権は発表者にあり、引用される場合「中日理論言語学研究会第63回研究会発表論文集」を明記すること
|