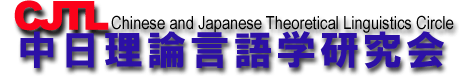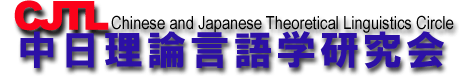|
第62回中日理論言語学研究会
日時:2024年09月21日(土)
場所:同志社大学大阪サテライト・オフィス
ご報告:
関係者の皆様へ:
先にご案内させていただきました第62回中日理論言語学研究会は、9月21日(土)に同志社大学大阪サテライト・オフィスにて開催され、40名の方々にご参加いただき、成功裡に終了いたしましたことをご報告申し上げます。
今回の研究会では、「可能と意志、表現と発話」というテーマをめぐり、シンポジウム形式で研究発表を行いました。冒頭では、沈氏のご挨拶の後、シンポジウムの座長である定延氏よりテーマの重要性と本研究の経緯についてご説明をいただきました。
井上氏は、可能文を潜在可能と実現可能に分けて考察し、中国語では可能文が潜在系可能のみを表すのに対し、日本語と韓国語の可能文は、潜在系可能も実現系可能も表すことができることを示されました。また、日本語と韓国語の可能文における実現可能の成立条件の違いについても指摘されました。日本語では期待通りの結果が実現した場合に可能文が用いられますが、韓国語では「阻害要因の克服」という意味が明確でなければ可能文は使用されないことを明らかにされました。
高山氏は、われわれの文法記述が現実世界とどのように結びついているかを、「意志」と「可能」を例に挙げて考察し、提言されました。従来の日本語の記述文法では、「意志」は「基本形/ウ/ヨウ/ム(古典語)」などが表す文法的意味として、「行為に先行する心的状態」とされますが、実際の感覚では「意志」という概念の実在は明確ではなく、日常のどの場面で必要なのかも理解しにくいとのことです。「意志」は〈意図〉〈願望〉〈信念〉といった要素によって構成される複合概念であり、行為の側面として捉えることができます。また、行為の実現においては〈可能〉と深く関わっており、文法研究が現実世界から乖離しないためには、生活の場面から形式を見ていく実践重視の観点が必要であると主張されました。
定延氏は、話者のエゴフォリシティに基づく文法記述の必要性を説きました。話者のエゴフォリシティは、「自己の内面を感じる」体験発話と「他者の外面を眺める」体験表現に分かれますが、今回は「他者の外面を眺める」体験表現に焦点を当て、「モノの到着を着点視座で表す『来る』表現」、「力の到着を着点視座で表す『(ら)れる』表現」、「利益の到着(発生)を着点視座で表す『くれる』表現」について具体例を挙げて解説されました。これらの表現が、それぞれの視座からの「眺め」と密接に結びついていることを示し、体験表現の特質を帯びていることを明らかにされました。
発表者間での活発な議論に加え、フロアからも多くの質問やコメントが寄せられ、非常に盛況な会となりました。
次回の第63回中日理論言語学研究会は、2025年1月に開催予定です。詳細は追ってご連絡させていただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
それでは、今後ともご指導・ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
<発表者及び発表題目(敬称略、順不同)>
(発表概要(PDF)を公開いたします)
井上 優(日本大学):
「可能文の意味について」(PDF)
高山 善行 (福井大学):
「文法研究は現実世界とどうつながるか?〈意志〉の問題を例に」(PDF)
定延 利之(京都大学):
「日本語の体験とエゴフォリシティ」(PDF)
※著作権は発表者にあり、引用される場合「中日理論言語学研究会第62回研究会発表論文集」を明記すること
|